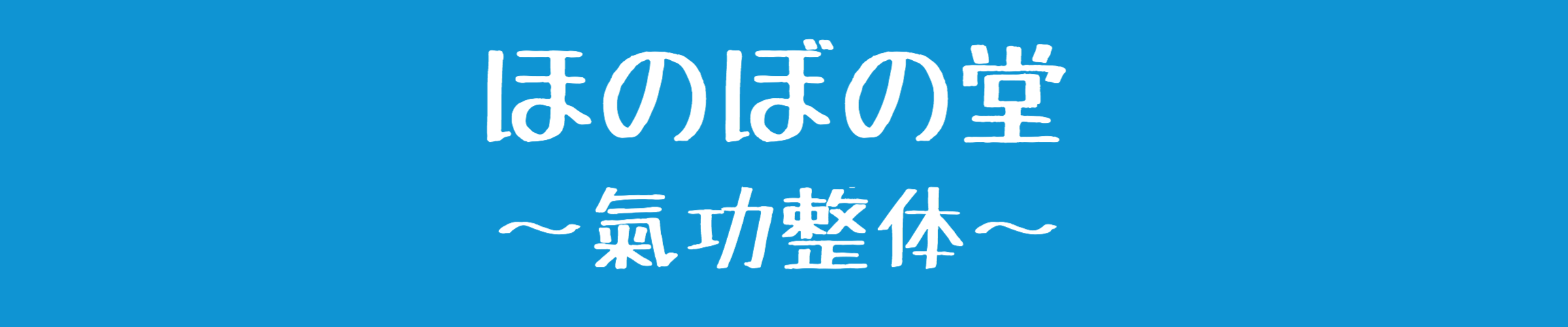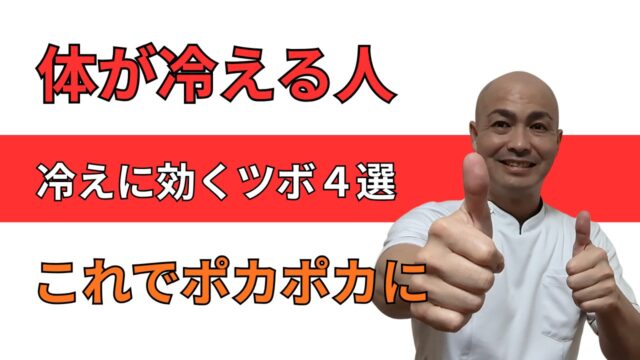「眠れない…」その不眠、実は胃腸の疲れと内臓の冷えが原因かも?整体師が教える快眠法
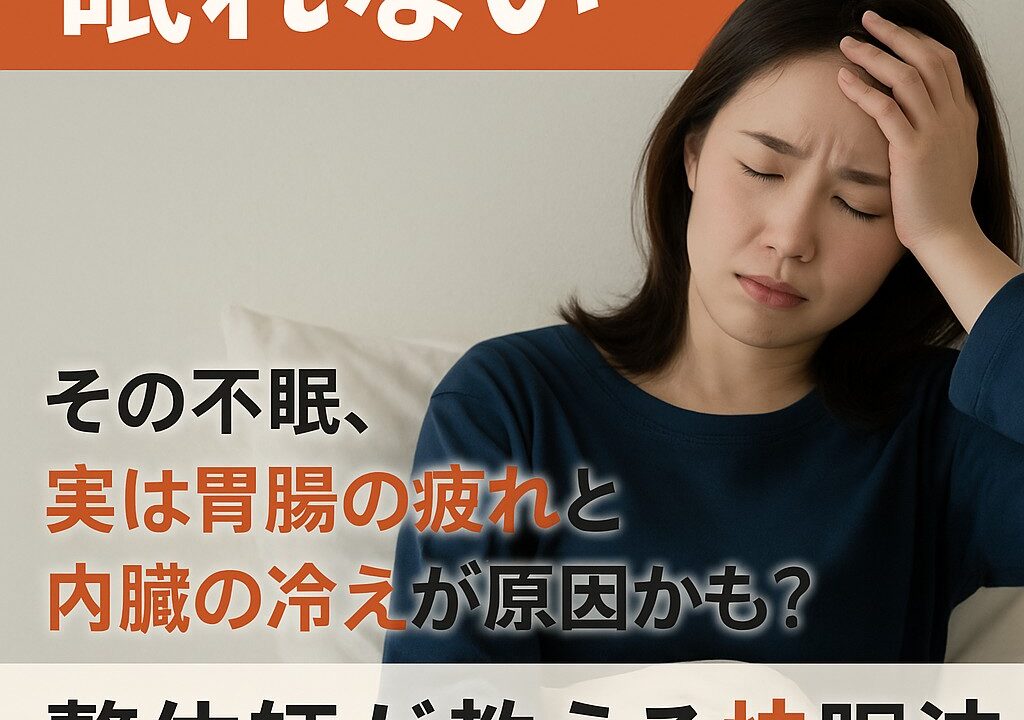
こんにちは。沖縄県の北谷町で整体師をしている比嘉です。
この記事では、不眠と胃腸の疲れと内臓の冷えがなぜ眠りに影響するのかについて解説します。
「夜なかなか寝付けずに悩んでいる方」
「自然な方法で自律神経を整え、快眠を目指したい方」
「胃腸の不調(重だるさ、食欲不振)が続いている方」
あなたは、以下のような悩みを抱えていませんか?
「寝つきが悪い」
「夜中に目が覚める」
「朝までぐっすり眠れない」
もしかしたら、その不眠の原因は、胃腸の疲れや内臓の冷えが関係しているかもしれません。
不眠というと、ストレスや自律神経の乱れが原因と思われがちです。
しかし、東洋医学では内臓の状態も深く関わっていると考えられています。
特に、胃腸の疲れや冷えは、自律神経のバランスを崩し、眠りの質を下げてしまう大きな要因の一つ。
この記事では、不眠と胃腸の関係、内臓の冷えがなぜ眠りに影響するのか、整体師としてのアプローチや、自宅でできるセルフケアまでお伝えします。
自律神経と不眠の関係については以下の記事で詳しく記しています。
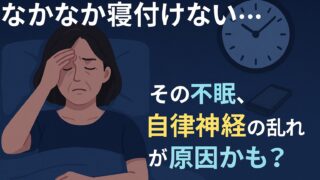
なぜ胃腸の疲れや内臓の冷えが不眠につながるのか?
私たちの体は内臓と自律神経が密接に関わっています。
特に胃腸は「第二の脳」とも呼ばれ、自律神経の働きと深く結びついています。
自律神経と胃腸の関係
自律神経には、昼間活動する「交感神経」と、夜リラックスする「副交感神経」があります。
胃腸はこの副交感神経が優位なときに活発に働き、消化・吸収・回復を行います。
しかし、胃腸が疲れていたり、冷えていたりすると、内臓の働きが弱まり、夜になっても副交感神経が優位になりづらくなります。
その結果、体がリラックスできず、眠りの質が低下するケースがあります。
東洋医学から見る「脾(ひ)」と「腎(じん)」
東洋医学では、胃腸の働きを「脾(ひ)」、内臓の温めを「腎(じん)」が担っていると考えます。
-
脾が弱ると、食べ物の消化吸収がうまくいかず、体に余分な水分や老廃物が溜まりやすくなります(これが冷えにつながります)。
-
東洋医学では、腎は体の「熱源」とされており、特に下半身の冷えと深く関係しています。腎の力が弱まると、身体を温める力(陽気)が不足し、足腰の冷えや全身の代謝が落ちることで、結果的に胃腸など内臓の働きにも影響を与えると考えられています。
この脾と腎のバランスが崩れると、胃腸の調子が悪くなり、結果的に不眠が引き起こされるとされています。
胃腸の疲れや内臓の冷えを改善する整体アプローチ
当院「ほのぼの堂~氣功整体~」では、こうした不眠の原因を自律神経の調整と氣功整体で経絡・ツボを刺激する施術でアプローチしています。
経絡・ツボ刺激で内臓を活発に
胃腸の経絡(脾経・胃経)や、腎の経絡(腎経)にアプローチすることで、内臓の働きを活発にし、自律神経のバランスを整えます。
特に、不眠には以下のツボが有効です。
-
足三里(あしさんり):胃腸の働きを整える
-
三陰交(さんいんこう):血流を促し、内臓を温める
-
湧泉(ゆうせん):腎を活発にして冷えを改善する
これらを刺激し、体のエネルギー(氣)の巡りを整えていくことで、内臓の状態が改善され、自然と眠れる体質へと導きます。
不眠に効果が期待できるツボの説明は、以下の記事で詳しく述べています。
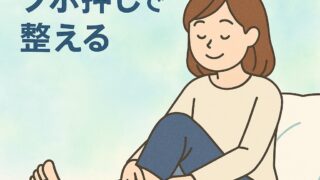
自宅でできるセルフケア
以下では、自宅でできるセルフケアについて記します。
1. 夕食は就寝2~3時間前までに
夜遅くの食事は胃腸に負担がかかります。
消化が終わらないまま寝ると、内臓が休まらず、自律神経も乱れがちに。
できれば就寝2~3時間前までに夕食を済ませ、内臓が休める時間を作りましょう。
2. 寝る前は白湯やハーブティーで内臓を温める
内臓の冷えは不眠の原因になります。
寝る前に白湯(さゆ)や、カモミールなどリラックス効果のあるハーブティーを飲むことで、内臓を内側から温め、副交感神経が優位になりやすくなります。
3. 足湯や腹巻きもおすすめ
冷えが強い方は、足湯や腹巻きでお腹や足元を温めると、内臓までじんわり温まります。
まとめ:不眠は「内臓」から見直してみよう
不眠の背景には、胃腸の疲れや内臓の冷えが潜んでいることがあります。
自律神経や内臓の状態を整えることで、薬に頼らず自然な眠りを取り戻せる可能性があります。
もし、セルフケアをしても改善が見られない場合は、整体などの専門的なケアを受けてみるのも一つの方法です。
ほのぼの堂~氣功整体~へのご案内
当院「ほのぼの堂~氣功整体~」では、自律神経の調整と内臓の働きを活発にする施術を行っています。
お気軽にご相談ください。
当院独自の氣功整体で、心身ともにリラックスして、ぐっすり眠れる毎日をサポートします。
📅 ご予約はこちらから:
▶ 【ご予約専用ページ】
(受付時間:8:00~20:00 / 定休日:火曜日)